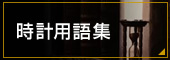これまでの連載を通じて数多くの靴を紹介してきたが、最終回は誰もが憧れる「究極の靴」 について考えていきたい。この「究極」という言葉には、さまざまな解釈が存在するが、事靴に関して言えば、やはりパーソナルオーダー、いわゆるビスポークのくつということになるだろう。このビスポークとは顧客が店主に話しかけられながら(=be spoken)、オーダーのスーツを仕立てたことが語源とされる。 注文主の足の形を詳細に計測し、忠実に再現した木型を製作。これを元に作られた靴であれば、足にフィットした、まさに理想の靴になるというわけだ。 靴作りが産業として大きな発展を遂げたのは19世紀末。革を縫い合わせるミシンが発明されたことがきっかけだった。それ以前は靴は当然、手縫いによる少量生産、靴職人の技術や個性が問われる時代でもあった。 その後、グットイヤー式やマッケイ式と呼ばれる機械式製靴技術の普及により、手作り靴は高級既成靴へと転換。ところが1970年代に今度は科学技術の進歩により、底付けにコストの安い接着剤が導入されると、手作業による底付け革靴は駆逐されてしまう。しかし1990年代に入るとその反動か、再び縫製による高級既成靴の見直しが始まり、その流れがビスポークにも波及。今日ではしずかなブームとも呼べる状況になっている。 さて、このような事象だけを並べてみると「歴史は繰り返される」的な印象をもたれるかもしれない。しかし、私は個人的に今日の状況は「ビスポーク・ルネッサンス」とも呼べる状況だと考えている。その象徴的存在が、右ページで紹介している『福田洋平』ブランドの靴だ。 その最大の特徴は木型のシェープ。木型は注文主の足のデータを元に作られるが、人間の足は工業規格品ではない。なかには均等の取れていない足の持ち主もいるだろうし、足の左右で微妙に大きさも違うかもしれない。ゆえにデータだけで木型を作れば、なんともバランスの悪い靴が出来上がってしまうおそれもある。もちろん、従来もそんなバラツキ加味して製作してきたのだが、福田氏は、それをさらに追求。計測データ重視の木型作りではなく、基本木型の研究から着手し、独自の世界を作り上げた。 あえて表現するのであれば、高級既成靴とビスポーク、それぞれ木型の長所を非常に高い次元で融合させたとでも言うべきか。具体的には履き口を広く、足を包み込むように靴の内底を深くしたこと。これらはすべて、履きやすさ・歩きやすさを考えてのこと。実は今回、メインで取り上げているのは私が福田氏にオーダーした靴なのだが、その仕上がりは「注文主の歩く癖を踏まえて靴を作っている」と思わせるほど。 しかも、そんな木型作成からデザインまで彼一人で手がけてしまうのも素晴らしい。これまで700足以上の靴を履いてきた私の経験からも、その品質はワールドクラス。靴の本家、イギリスをもしのぐといっても過言ではない。 そんな靴が日本人の手によって誕生したことを何よりの喜びとしながら、この連載を終えたいと思う。

 これまでの連載を通じて数多くの靴を紹介してきたが、最終回は誰もが憧れる「究極の靴」 について考えていきたい。この「究極」という言葉には、さまざまな解釈が存在するが、事靴に関して言えば、やはりパーソナルオーダー、いわゆるビスポークのくつということになるだろう。このビスポークとは顧客が店主に話しかけられながら(=be spoken)、オーダーのスーツを仕立てたことが語源とされる。 注文主の足の形を詳細に計測し、忠実に再現した木型を製作。これを元に作られた靴であれば、足にフィットした、まさに理想の靴になるというわけだ。 靴作りが産業として大きな発展を遂げたのは19世紀末。革を縫い合わせるミシンが発明されたことがきっかけだった。それ以前は靴は当然、手縫いによる少量生産、靴職人の技術や個性が問われる時代でもあった。 その後、グットイヤー式やマッケイ式と呼ばれる機械式製靴技術の普及により、手作り靴は高級既成靴へと転換。ところが1970年代に今度は科学技術の進歩により、底付けにコストの安い接着剤が導入されると、手作業による底付け革靴は駆逐されてしまう。しかし1990年代に入るとその反動か、再び縫製による高級既成靴の見直しが始まり、その流れがビスポークにも波及。今日ではしずかなブームとも呼べる状況になっている。 さて、このような事象だけを並べてみると「歴史は繰り返される」的な印象をもたれるかもしれない。しかし、私は個人的に今日の状況は「ビスポーク・ルネッサンス」とも呼べる状況だと考えている。その象徴的存在が、右ページで紹介している『福田洋平』ブランドの靴だ。 その最大の特徴は木型のシェープ。木型は注文主の足のデータを元に作られるが、人間の足は工業規格品ではない。なかには均等の取れていない足の持ち主もいるだろうし、足の左右で微妙に大きさも違うかもしれない。ゆえにデータだけで木型を作れば、なんともバランスの悪い靴が出来上がってしまうおそれもある。もちろん、従来もそんなバラツキ加味して製作してきたのだが、福田氏は、それをさらに追求。計測データ重視の木型作りではなく、基本木型の研究から着手し、独自の世界を作り上げた。 あえて表現するのであれば、高級既成靴とビスポーク、それぞれ木型の長所を非常に高い次元で融合させたとでも言うべきか。具体的には履き口を広く、足を包み込むように靴の内底を深くしたこと。これらはすべて、履きやすさ・歩きやすさを考えてのこと。実は今回、メインで取り上げているのは私が福田氏にオーダーした靴なのだが、その仕上がりは「注文主の歩く癖を踏まえて靴を作っている」と思わせるほど。 しかも、そんな木型作成からデザインまで彼一人で手がけてしまうのも素晴らしい。これまで700足以上の靴を履いてきた私の経験からも、その品質はワールドクラス。靴の本家、イギリスをもしのぐといっても過言ではない。 そんな靴が日本人の手によって誕生したことを何よりの喜びとしながら、この連載を終えたいと思う。
これまでの連載を通じて数多くの靴を紹介してきたが、最終回は誰もが憧れる「究極の靴」 について考えていきたい。この「究極」という言葉には、さまざまな解釈が存在するが、事靴に関して言えば、やはりパーソナルオーダー、いわゆるビスポークのくつということになるだろう。このビスポークとは顧客が店主に話しかけられながら(=be spoken)、オーダーのスーツを仕立てたことが語源とされる。 注文主の足の形を詳細に計測し、忠実に再現した木型を製作。これを元に作られた靴であれば、足にフィットした、まさに理想の靴になるというわけだ。 靴作りが産業として大きな発展を遂げたのは19世紀末。革を縫い合わせるミシンが発明されたことがきっかけだった。それ以前は靴は当然、手縫いによる少量生産、靴職人の技術や個性が問われる時代でもあった。 その後、グットイヤー式やマッケイ式と呼ばれる機械式製靴技術の普及により、手作り靴は高級既成靴へと転換。ところが1970年代に今度は科学技術の進歩により、底付けにコストの安い接着剤が導入されると、手作業による底付け革靴は駆逐されてしまう。しかし1990年代に入るとその反動か、再び縫製による高級既成靴の見直しが始まり、その流れがビスポークにも波及。今日ではしずかなブームとも呼べる状況になっている。 さて、このような事象だけを並べてみると「歴史は繰り返される」的な印象をもたれるかもしれない。しかし、私は個人的に今日の状況は「ビスポーク・ルネッサンス」とも呼べる状況だと考えている。その象徴的存在が、右ページで紹介している『福田洋平』ブランドの靴だ。 その最大の特徴は木型のシェープ。木型は注文主の足のデータを元に作られるが、人間の足は工業規格品ではない。なかには均等の取れていない足の持ち主もいるだろうし、足の左右で微妙に大きさも違うかもしれない。ゆえにデータだけで木型を作れば、なんともバランスの悪い靴が出来上がってしまうおそれもある。もちろん、従来もそんなバラツキ加味して製作してきたのだが、福田氏は、それをさらに追求。計測データ重視の木型作りではなく、基本木型の研究から着手し、独自の世界を作り上げた。 あえて表現するのであれば、高級既成靴とビスポーク、それぞれ木型の長所を非常に高い次元で融合させたとでも言うべきか。具体的には履き口を広く、足を包み込むように靴の内底を深くしたこと。これらはすべて、履きやすさ・歩きやすさを考えてのこと。実は今回、メインで取り上げているのは私が福田氏にオーダーした靴なのだが、その仕上がりは「注文主の歩く癖を踏まえて靴を作っている」と思わせるほど。 しかも、そんな木型作成からデザインまで彼一人で手がけてしまうのも素晴らしい。これまで700足以上の靴を履いてきた私の経験からも、その品質はワールドクラス。靴の本家、イギリスをもしのぐといっても過言ではない。 そんな靴が日本人の手によって誕生したことを何よりの喜びとしながら、この連載を終えたいと思う。